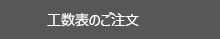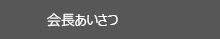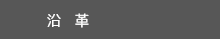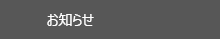| 名称 | 全国大型自動車整備工場経営協議会(全大協) |
|---|---|
| 本部所在地 |
〒143-0023 東京都港区芝浦4-16-25 (安全自動車株式会社 内) TEL:03-6327-3334 |
| 会長 | 本島 誠之 (株式会社モトシマ 代表取締役社長) |
設立の背景と経緯
全国大型自動車整備工場経営協議会(通称:全大協)は、1979年4月20日、米国BEAR社製フレーム修正機を導入し、車体整備・架装を専門とする全国の整備 工場31社が集結して設立された団体です。
設立当初は、フレーム修正に関する技術研究を主目的とする研究会としてスタートしました。業界の高度化・多様化を背景に、会員企業が世界最先端の技術・設備・ 工具の視察・導入を図るべく、毎年海外研修を実施するなど、活動の幅を広げてきました。
「標準作業時間参考資料」作成への歩み
会員各社が設備と技術を整備する中で、作業の標準化・見積りの透明化に対する社会的ニーズが高まり、全大協では「標準作業時間参考資料(工数表)」の整備 が重要なテーマとなりました。これは、作業ごとにかかる時間を妥当な形で数値化し、損保会社・ユーザー双方が納得できる修理見積りのベースを確立する目的でスタートしたものです。
この資料作成にあたっては、故岩崎貫一氏(岩崎自動車工業)や綿谷好三氏(ワタヤ自動車)といった先駆者の尽力がありました。とりわけ綿谷氏は昭和23年か ら自動車交通事故車鑑定人として活動しており、昭和42年には小型車用の指数表を作成。これが損保団体にも認められたことで、大型車においても妥当性ある工 数表作成の機運が一気に高まりました。
昭和54年には全大協内に「標準作業時間研究委員会」が設立され、昭和54年12月には『中型車・大型車標準作業時間参考資料』の初版が発行。その後も新型車や 制度変更に応じて改訂を重ね、平成6年には小型貨物車も対象とするなど、現在 に至るまで幅広い車両に対応する資料として発展しています。
現在では、JIS Z8141:2001(日本工業規格)を基準とし、作業ごとの主作業時間と準備時間、さらには高所作業等の法令・作業安全・難易度まで加味した「事故 車損害算定参考資料」として、実情に即した活用がされています。
全大協の理念と社会的使命
全大協は、大型自動車の整備を通じて「物流・運輸資源としての大型車両」を効率的に稼働させることで、国内の環境保全・地域経済の活性化に貢献することを理念としています。 現代社会は「情報過多の中の情報不足」とも言われ、地域に根ざした自動車整備業が埋もれがちです。そうした中で、業界を支える全国的な組織として、以下の3つを軸に活動を行っています。
・情報の共有
・技術の相互研鑽
・新技術の導入・開発
また、単なる国内活動にとどまらず、世界からの学びと交流を通じた「グローバルなローカリゼーション」も目指しています。
国際的な連携とAIRC(車体修理国際会議)
全大協は、車体修理業界の国際的協調を目的とするAIRC(Auto Body International Repair Conference:車体修理国際会議)とも深い関係を持っています。AIRCにはアメリカ・ヨーロッパ・オーストラリア・ニュージーランドなどの代表的な車体整備団体が加盟しており、全大協の理事でもあり第2代会長を務めた丸山憲一氏がAIRC副会長に就任したことを契機に、密接な連携を維持してきました。 AIRCでは、各国間の修理技術・制度・設備の情報交換や、事故車の検査制度に関する議論、さらには環境問題への対応などが議題となっており、日本の技術・制度の国際標準化に向けた提案も行われています。
今後の展望
近年、自動車業界では自動運転やAI技術などによって構造が大きく変化しています。車両の高度化に伴い、整備技術もますます複雑かつ高度な対応が求められています。 全大協では、今後も以下のような課題に真摯に取り組み、業界の発展と社会的信頼の向上を目指してまいります。
・正確で実用的な標準作業時間資料の作成・改訂
・次世代車両への対応を見据えた技術研修・設備導入
・国内外の情報収集と人的交流の強化
・地域社会と国際社会の橋渡し役としての機能強化
対応エリア
北海道・東北
北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県
関東
茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県
北陸・信越
新潟県/富山県/石川県/福井県/山梨県/長野県
東海
岐阜県/静岡県/愛知県/三重県
近畿
滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県
中国
鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県
四国
徳島県/香川県/愛媛県/高知県
九州・沖縄
福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県